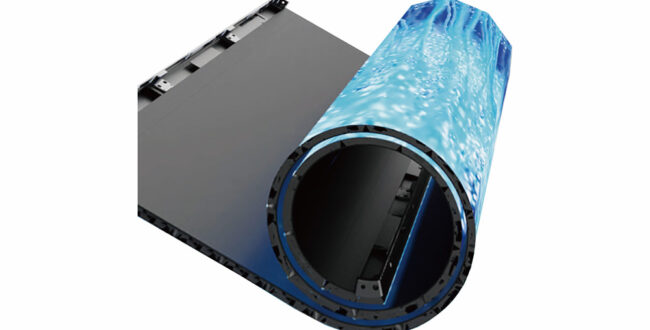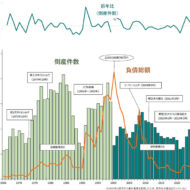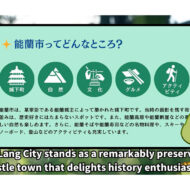魅せる筆文字
提灯や千社札に書かれる芝居文字(勘亭流)や寄席文字(橘流)などの文字を総称して「江戸文字」と呼ぶ。町火消しの纏(まとい)や半纏といった染物文化により熟成していった江戸文字。その中で、提灯に書かれることの多い書体が、かご文字だ。
かご文字は、最初に輪郭線を書いてから中を塗るという独特の手順で書く。「かご」という名前の由来は、筆を入れる輪郭の線が編んだかごのように見えるから、との説が有力である一方、町火消しの纏に書かれる文字という由縁から、「ご加護がありますように」とゲンを担いでかごの名がついたとの説もある。
福島さんは、このかご文字をベースに、オリジナルの書体「魅せる筆文字」を考案している。
遠くから見て映えるよう太さと隙間のバランスを調整したもので、長年の研鑽から生み出された実用書体だ。
福島さんは現在、この魅せる筆文字と江戸文字や楷書文字を網羅した書体見本帳を執筆中だという。当用漢字と人名漢字合わせて約1万字を収録し、年内の発行を予定している。
これからも需要が続く限り続けたいと話す福島さんの元へは、わびさびを求め店舗デザイナーも訪れる。祭だけではなく、新しくオープンする居酒屋など、凝った内装演出にも採用される機会が増えてきているのだ。
取材の最後、手書き提灯の魅力を聞いた。「“粋”だね、江戸の粋。そんな感じ」福島さんはそう言ってはにかむように笑った。

ビニール提灯に文字を書き込む場合は、畳んだ際に塗料同士が癒着しないよう、調合した塩ビ塗料を使う。その割合は企業秘密だ

灯を入れた際にムラが出ないよう、2回から3回ほど重ね塗りをする。福島さんは、雨や湿気を防ぐ仕上げのエゴマ油を塗る前に、紫外線を防ぐ劣化防止剤を塗る一手間を加えている。
手書き屋 福島栄峰