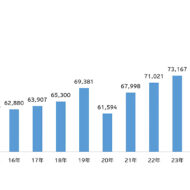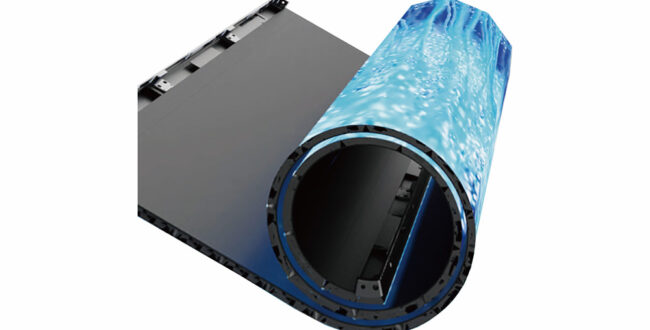河南工場操業(2004年):本社工場を府中市河南町へ移転した
バブル期の求人難には職場改善で社員を確保
苦節の時代が過ぎ、1980年代に入って、サイン業界におけるIT化の口火とも言える「カッティングマシン」が登場。筆文字一つで数千円の受注単価に対して、1台で500万円と、イニシャルコストは経営をひっ迫させかねないほどに高額だったが、手書きは無くなりはしないが徐々に置き換わっていくだろうという先見の明で、無理を承知で他社に先駆け導入を決めた。
当時はマシンの運用自体が革新的だった時代。数少ない導入企業も、社長が自ら操作するのが一般的だったが、分業の必要性を感じ、ワープロを簿記で日常的に使っている商業高校卒の女性社員を採用した。女性を雇用することは、3Kのイメージが強い業界のイメージを払拭(ふっしょく)する狙いもあった。現場を任せたことで、自分は職人ではなく経営者に専念して、営業に注力し、多数の案件獲得につながった。
一見、会社運営は軌道に乗ったかに見えたが、新たな問題も噴出した。仕事が増えていく中で、新たに人を雇うが、数年で辞めてしまうことが繰り返された。業界の恒常的な問題でもあるが、社員の定着率の低さは地域や時代を問わず、経営者にとっては常に付きまとう悩みの種。立石氏は、「コミュニケーションも定期的に取っているつもりで、何が原因か分からなかった。むしろ去っていく者にやる気がないからだと決めつけていた」と述懐する。
その後、時代はバブル期に突入し、景気上昇とともに、3Kのイメージが強く魅力が薄い業界ではさらに雇用確保が難しくなり、仕事はあるが人は集まらない、要因は違えど、働き手不足の現在と同じような状況に至った。
転機となったのは、経営理念を諭された税理士に渋々連れて行かれた勉強会でのこと。講演で「経営者にとって一番の仕事は社員に夢を与えることだ」と聞き、目が覚めた。コストをカットし、いかに利益を残すかが経営者の力量ではなく、社員にいかに利益を還元させるかが経営者の役目だと思い知らされた。
以前は、自分にとって都合の良い「立石労働基準法」を作り、社員には社会保険も福利厚生も皆無だった。職人気質の職場では、社員はドラム缶の上で昼食をとるのが当たり前。残業があっても、規定分しか賃金を支払わないのも、仕事が未熟なのだから当然のことだと思っていた。
しかし、人が辞めていく要因は自分にあるのだと、ここで心を入れ替え、ストーブを置いた簡易な休憩スペースを設けるなど、まずはできることから職場環境の改善に取り組んだ。「社員にこの頃変わったなと言葉をかけたら、社長が変わったんですよと返された。経営者が変わらなければ、会社は変わらないことをこの時、実感した」。